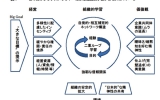米トヨタなど米国企業がDEIから撤退を始めている

Afif Ahsan/iStock
1月12日の産経新聞は、「米マクドナルドも『多様性目標』を廃止 トランプ次期政権発足で見直し加速の可能性」というヘッドラインで、米国の職場における女性やLGBT(性的少数者)への配慮、『ポリティカルコレクトネス(政治的公正)』の行き過ぎによりさまざまな弊害が出ており、これに反対する動きが始まっていると報じた。
米国企業が進めるDEIからの撤退
米国のマクドナルドは、米国内の法的環境の変化を理由に、以下の変更を発表している。
- 米国内のリーダーシップ層における「過小評価されているグループ」の比率を2025年末までに35%にするという目標を撤回
- サプライヤーに対するDEI(Diversity, Equity and Inclusion; 多様性、公平性、包摂性)要件の廃止
- 「多様性チーム」を「グローバル・インクルージョン・チーム」に改称し、外部の多様性調査への参加を一時停止
マクドナルドは、これらの変更後も包摂性へのコミットメントは揺るぎないと強調したが、米国内では同様の動きが見られ、DEI施策の見直しが進行している。
Epoch Timesなどによれば、米国での同様の動きは、キャタピラー、フォード、ハーレーダビッドソン、ディア・アンド・カンパニー、モルソン・クアーズ、トラクター・サプライ、ジョン・ディア、ロウズ、ブラウン・フォーマン、スタンレー・ブラック・アンド・デッカー、トヨタ、ボーイング、ウォルマート、メタなどでも見られており、DEIからの撤退や取り組みの縮小が進んでいるということだ。
これらの企業の幹部は、DEIというイデオロギーに現を抜かすのではなく、顧客に目を向け、優れた商品やサービスを提供することこそが、株主の価値を創造することであるという本来の姿に戻ろうとしている。
ESGの推進者だった米大手投資企業ブラックロックのフィンクCEOでさえ、「政治的」になりすぎたとしてDEIを見捨てた。他の大企業は、DEIへの取り組みを完全には覆していないにもかかわらず、それを軽視している。
つまり、DEIやその他のソーシャル・イニシアチブは「徒花」であり、企業の収益にプラスになることもなければ、効率性を向上させることもない。実際、DEIイニシアチブは時間、資金、その他のリソースを浪費する。
企業が優れた人材を採用・維持し、従業員を公平に扱うためには、企業は多様性に係る責任者を置いたり、感受性トレーニングを行ったり、ノルマを課すなど行っているが、そんなものは必要としないということだ。
この動きは、消費者にとっても、ますます「政治家」する職場で働かなければならなかった100万人の労働者にとっても朗報だという。
米トヨタ、昨年10月、DEIに関する方針の見直しを発表
米国全土で企業が社会的活動から核心ビジネス目標へと焦点を移す動きがある中、米トヨタは、昨年10月にDEI活動の一部を縮小し、LGBTイベントへのスポンサーシップを停止し、外部ランキングから撤退すると発表した。
それまでの米トヨタは、DEIへの強いコミットメントを反映しており、昨年6月に更新された最新のサステナビリティ計画には、人種、性別、性的指向に基づき労働力の構成を変えることを目的とした多様性の取り組みが含まれていた。
この計画には、2014年と比較して2030年までに管理職の女性の数を5倍に増やすなどの女性スタッフの採用目標が含まれている。また、「無意識の偏見」トレーニングや、管理職の進捗を追跡するためのDEIスコアカードなどの取り組みが強調されており、反DEI活動家から、「ウォーク(WOKE=社会問題などへの意識高い)系」ポリシーに焦点を当てている企業として批判されていた。
しかし、現在の米トヨタは、STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)教育や労働力に特化した活動に絞り、プライドパレード(LGBT文化を称えるパレード)などの文化イベント支援を終了すると従業員に通知した。また、トヨタ・ビジネスパートナリンググループを再編成し、専門能力開発やビジネス推進を重視する方針を打ち出した。
さらに、米トヨタはHRCの企業平等指数において完璧なスコアを獲得していたが、こうした平等指数など、第三者ランキングへの参加を終了することも決定した。
米トヨタの方針変更の発表を受け、「企業の中立性が確保されれば、消費者の核心的な信念を侵害しないため、ビジネスは成功するだろう」という歓迎の声も聞かれる。
米トヨタも反DEI活動家からの批判をかわそうとして、発表した方針転換ではないのだろうが、企業サイトには、いまでもDEIの大切さが記載されている。
Toyota USA | Diversity and Inclusion
今後、米トヨタがどのように多様性とビジネス目標のバランスを取っていくのかが注目される。
トヨタ自動車の公式見解
トヨタ自動車の公式企業サイトには、ESG:社会のひとつとして、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)について、以下が記載されている。
【ありたい姿】
・自動車会社からモビリティカンパニーへの転換に向けた従来領域のたゆまぬ変革と新領域へのチャレンジに取り組み、多様な才能や価値観を持つ人材が最大限能力を発揮
【取り組み事項】
・多様な生き方・働き方を尊重し、一人ひとりの意欲・能力に応じた活躍機会を提供
・性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、障がい、配偶者や子の有無などを含むいかなる理由であれ差別を認めない
・ハラスメントのない、風通しの良い職場づくり
我が国の政府や財界、マスコミなどは、今でもDE&Iを強化しようとしている。そうした国内の空気を読んだうえで、この公式企業サイトは書かれているのであろう。奥歯に物が挟まったような微妙な言い回しになっており、具体的なことは何も語っていない。
米国と同じく、我が国でもDEIやその他のソーシャル・イニシアチブがビジネスを進めていくうえでの「徒花」だとしたら、菅首相の「ネットゼロ、カーボンニュートラル」宣言に反対した豊田氏のように、DEIというイデオロギーに対してもトヨタ独自の撤退宣言を行うという気骨を示して欲しいものである。

関連記事
-
2025年7月31日の北海道新聞によると、「原子力規制委員会が泊原発3号機(後志管内泊村)の審査を正式合格としたことを受け、北海道電力は今秋にも電気料金の値下げ幅の試算を公表する」と報じられた。北海道電力は2025年8月
-
「甲状腺異常が全国に広がっている」という記事が報道された。反響が広がったようだが、この記事は統計の解釈が誤っており、いたずらに放射能をめぐる不安を煽るものだ。また記事と同じような論拠で、いつものように不安を煽る一部の人々が現れた。
-
米国では発送電分離による電力自由化が進展している上に、スマートメーターやデマンドレスポンスの技術が普及するなどスマートグリッド化が進展しており、それに比べると日本の電力システムは立ち遅れている、あるいは日本では電力会社がガラバゴス的な電力システムを作りあげているなどの報道をよく耳にする。しかし米国内の事情通に聞くと、必ずしもそうではないようだ。実際のところはどうなのだろうか。今回は米国在住の若手電気系エンジニアからの報告を掲載する。
-
米国トランプ政権は4月8日、「美しいクリーンな石炭産業の再活性化」というタイトルの大統領令を発し、石炭を国家安全保障と経済成長の柱に据え、その推進を阻害する連邦規制を見直すこと、国有地での鉱区の拡大、輸出の促進などを包括
-
COP30に参加してきた。今回の開催地はブラジルのアマゾン河口に近い地方都市ベレン。宿泊施設1万床といわれるこの町で例年4~5万人が押し掛けるCOPが開催されるということで、ブラジル政府は民泊や仮設宿泊所、ひいては大型ク
-
福島第1原子力発電所の事故以降、メディアのみならず政府内でも、発送電分離論が再燃している。しかし、発送電分離とは余剰発電設備の存在を前提に、発電分野における競争を促進することを目的とするもので、余剰設備どころか電力不足が懸念されている状況下で議論する話ではない。
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑪:災害のリスクは減り続けている) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表
-
日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間