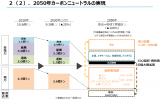米国エネルギー長官、アフリカに化石燃料が必要と説く
米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。

クリス・ライトエネルギー長官
(米国マリ大使館HPより)
アフリカの開発のためには、天然ガスも、石炭も、あらゆるエネルギーを活用すべきだ、というものだ。一部、邦訳しよう:
ワシントンでは、ここ数年、より多くのエネルギーを生産するのではなく、より生産を少なくしようとするエネルギー政策を採ってきた。 再生可能エネルギー以外のあらゆるエネルギーを禁止または規制しようとする、包括的ではなく、排他的なエネルギー政策が採られた。
排他的なエネルギー政策は、アフリカ大陸を含む、世界中の何十億という人々から、生活を支えるエネルギーとエネルギー利用技術を遠ざけてきた。
トランプ大統領のリーダーシップのおかげで、排他的なエネルギー政策は終わり、包括的なエネルギー政策になった。乏しさではなく、豊かさの日々がはじまった。それは人々を最優先する日々だ。
具体的にはどういうことか? 米国の過去の数十年を振り返ってみよう。石炭は環境にやさしくないからといって、禁止したのか? そうではない。最もクリーンな化石燃料である天然ガスへの依存度が高まるなかでも、人々の創意工夫によって石炭はよりクリーンなエネルギーになり続けた。天然ガスが枯渇し始めたとき、われわれは配給をはじめたのか? そうではなく、シェール技術によって生産量を増やした。私はよく知っている。その革命の最前線にいたからだ。私はシェールビジネスを30年前に始めた。
「ネット・ゼロ(=CO2ゼロのこと)は邪悪な目標だ」と述べて環境運動家からは批判を浴びたクリス・ライト長官であるが、この講演でも言っていることは一貫している。化石燃料を使って経済開発を進めることこそ、正義だというものだ。
なおクリス・ライトはエネルギーと脱炭素政策に関して分厚い報告書にまとめ深く考察している(こんなエネルギー長官は世界中で見たことがない)。これは以前に紹介したので、以下リンク先を参照されたい。
日本は、バイデン政権に同調する形で、CO2を理由に開発途上国の化石燃料事業への公的な支援を止めてしまい、そのままになってしまっている。だがかかる不正義は覆し、化石燃料事業への支援を再開すべきではないのか。
■

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd
-
猪瀬直樹氏が政府の「グリーン成長戦略」にコメントしている。これは彼が『昭和16年夏の敗戦』で書いたのと同じ「日本人の意思決定の無意識の自己欺瞞」だという。 「原発なしでカーボンゼロは不可能だ」という彼の論旨は私も指摘した
-
広島高裁の伊方3号機運転差止判決に対する違和感 去る12月13日、広島高等裁判所が愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し、運転の停止を
-
はじめに 経済産業省は2030年までに洋上風力発電を5.7GW導入し、さらに事業形成段階で10GWに達することを目標に掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を目指していた。その先陣を切ったのが2021年の第1回洋上風力入札
-
ドイツで高騰しているのはガスだけではなく、電気もどんどん新記録を更新中だ。 2020年、ドイツの卸電力価格の平均値は、1MW時が30.47ユーロで、前年比で7ユーロも下がっていた。ただ、これは、コロナによる電力需要の急落
-
今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か
-
『羽鳥慎一のモーニングショー』にみられる単純極まりない論調 東京電力管内で電力需給逼迫注意報が出ている最中、今朝(29日)私はテレ朝の「羽鳥慎一のモーニングショー」をみていました。朝の人気番組なので、皆さんの多くの方々も
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間