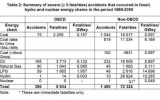中国の「2060年CO2ゼロ」地政学的な意味①日米欧の分断
国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的な効果を持っている。
これに対抗するために、日本は先ず第一に、地球温暖化を安全保障より重視する誤った世論を正す必要がある。

動画で演説した習近平氏(国連公式サイトより)
1. 習近平のCO2ゼロ宣言
2020年9月22日の国連総会の一般討論における習近平国家主席の演説が話題を呼んだ。内容は主にコロナ禍に関するものだったが、その中でCO2ゼロ宣言があったからだ。該当部分を抄訳すると以下のようになる:
気候変動に対処するためのパリ協定は、世界的な低炭素化の方向性を表しています。中国は、より強力な政策措置を採用し、2030年までにCO2排出量のピークに到達するよう努め、2060年までに炭素中立を達成するよう努めます。各国は、コロナ流行後の世界経済の「グリーン回復」を促進し、持続可能な開発のための強力な力を結集する必要があります。
ここで「炭素中立」と言っている意味は、化石燃料の燃焼によるCO2排出と、植林などによるCO2吸収を、差し引きゼロにする、という意味である。だいたいは、CO2排出をゼロにすること、つまりゼロエミッションと思ってよい。
今回の習近平の演説は、「多国間主義による国際協調」、「コロナ禍からのグリーン回復」、そして「ゼロエミッション」といった、近年になって欧州を中心に流行しているレトリックをそのまま踏襲したものだった。国連、欧州連合、英国および米国民主党の指導者は、相次いで、この演説を歓迎するコメントを出した。
ここのところ、南沙諸島での軍事基地建設、新彊における人権問題、香港における民主運動への対応、コロナ禍を巡る対応等で、相次いで国際的な非難を浴びてきた中国が、久しぶりに好感されることとなった。
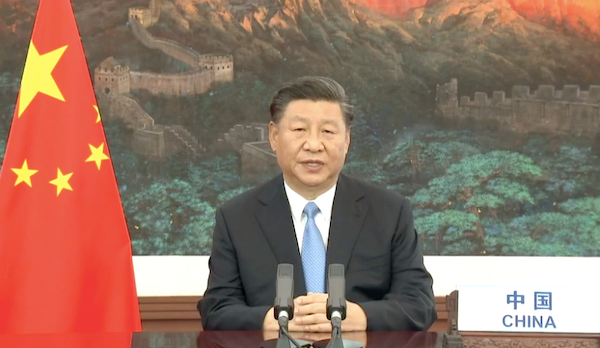
国連公式サイトより
2. 日米欧の分断
さて中国がゼロエミッションというポジションを取ったことで、日米欧では2つの分断が深まった。
第1は米国内の分断である。米国では地球温暖化問題は党派問題である。民主党は地球温暖化は深刻な脅威だとして、欧州と足並みをそろえて大幅に排出を削減すべきとしている。これに対して共和党は、地球温暖化はそれほど重大な脅威ではなく、極端な排出削減は必要無い、とする。とかくトランプ大統領だけが例外だと思われがちだが、決してそうではない。地球温暖化問題が論題に上れば上るほど、米国内の党派間の分断はますます深まる。
第2は自由陣営である米国と欧州の分断である。ドイツ・イギリスを始めとした豊かな欧州諸国では、環境運動の影響で、ここ数年で地球温暖化問題が政治的に最も重要な課題に押し上げられた。少なくとも、コロナ禍の直前まではそうだった。中国は、これに協力姿勢を見せることで欧州の好感度を増すことになり、米国共和党の非協力的な態度は欧州に嫌われることになる。
もともと、欧州の環境運動家は、中国に好意的な一方で、反米的な人が多い。歴史的に見ても、共産主義や社会主義の活動として反公害運動があり、その延長で環境運動が起きた。彼らは一貫して、資本主義を嫌い、その権化である米国を憎んできた。国際環境NGOは自由陣営の企業に強烈な圧力をかけてきたが、中国企業がその対象となることは無かった。
このように、中国にとってゼロエミッションというポジションを取ることは、孤立しがちだった国際社会からの好感を得るのみならず、米国内の分断を深め、また米欧の分断を深めるという効果がある。
情報戦によって、敵を一枚岩にせず、出来るだけ深刻な分断状態にすることは、国益を追求するための有効な手段となる。敵の団結を削ぐことで、人権、領土、技術、経済等にまつわるあらゆる国際問題に関する圧力を弱めることが出来るし、敵が国力を蓄えることも阻止できる。
このような戦術は、中国の軍人によって20世紀末に「超限戦」の一部として提言された。超限戦の思想では、平時においても、常に敵国と競争状態にあることを意識して、自国の国力増強と敵の分断化・弱体化を図る。中国はこれを実践してきたとされており、自由陣営ではシャドー・ウォー、ハイブリッド戦、グレーゾーン戦等と呼ばれて防衛のあり方が議論されてきた。
■

関連記事
-
アメリカは11月4日に、地球温暖化についてのパリ協定から離脱しました。これはオバマ大統領の時代に決まり、アメリカ議会も承認したのですが、去年11月にトランプ大統領が脱退すると国連に通告し、その予定どおり離脱したものです。
-
Caldeiraなど4人の気象学者が、地球温暖化による気候変動を防ぐためには原子力の開発が必要だという公開書簡を世界の政策担当者に出した。これに対して、世界各国から多くの反論が寄せられているが、日本の明日香壽川氏などの反論を見てみよう。
-
G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。 そこで成果文書を読んでみた。 ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、
-
日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。
-
5月23日、トランプ大統領は、 “科学におけるゴールドスタンダードを復活させる(Restoring Gold Standard Science)”と題する大統領令に署名した。 日本語(機械翻訳)は
-
15年2月に、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループで、高レベル放射性廃棄物の最終処分法に基づく基本方針の改定案が大筋合意された
-
GEPR・アゴラの映像コンテンツである「アゴラチャンネル」は4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送した。
-
政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間